リライト:ホームページの情報を整理する事も大切

2005年から WEB 業界一筋。500サイト超を手がける SEO・WordPress のエキスパート。「公開後こそ本番」を掲げ、データ分析とユーザー視点で成果を引き出す運用を提案。

2005年に制作会社へ入社後、プログラマーからキャリアをスタート。サーバー構築・データベース設計で培った技術を強みに、WordPress テーマ/プラグイン開発やサイト移行の難案件を多数担当してきました。
2010年以降は SEO エンジニアとしても活動領域を拡大。コンテンツ設計・内部リンク最適化・高速化チューニングにより、競合の激しいビッグキーワードで上位獲得を実現してきました。
現在は TREVO のウェブディレクターとして、要件定義から運用改善まで一気通貫でリード。AI ライティングや GA4/Looker Studio を活用したレポーティング手法を開発し、「数字で説明できるサイト運用」をポリシーにクライアントの ROI 最大化を支援しています。
趣味/強み:筋トレとランニングで日々の集中力をキープ。複雑な課題を“仕組み”で解決するのが得意。
モットー:「サイトは資産。改善を止めた瞬間から価値は目減りする」
SNS:x(旧 Twitter)@TREVO_WEB
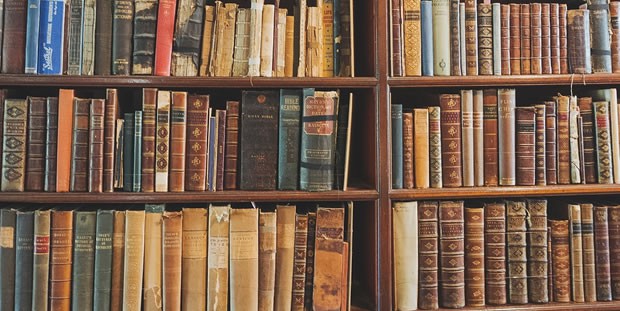
10年前(2014年頃)は、コンテンツをひたすら追加していくだけで、ある程度は検索エンジンからの流入を期待できる時代でした。しかし、年月が経つにつれ、メニューやバナーがどんどん増え、元の設計意図が崩れ、ユーザーが目的の情報にたどり着きにくくなるケースが多発していました。
こうした状況が長期化すると、サイト内で情報が散乱し、閲覧者に「混乱する」「わかりにくい」といったマイナスイメージを与えることもあります。実際、当時の私たちのサイトでも、追加に次ぐ追加で、ページ構成が複雑になり、見づらさや使いにくさが目立っていました。その結果、問い合わせ率が低下していたのです。
そこで2014年当時、全面リニューアルを行い、情報構造を整理した結果、お問い合わせ率のアップにつながりました。
ユーザーインターフェースが崩れる理由

当初は特定のコンテンツへスムーズに誘導する意図で設計されていたサイトでも、新サービスや新情報を優先的にアピールしようとコンテンツを増やしていくと、最初に引いた導線(ナビゲーション設計)が崩れがちです。
- 元々あったコンテンツが埋もれる
- 重要な情報がどこにあるのかわからなくなる
- 似たような主張をするページやリンクが増え、サイト全体の秩序が乱れる
こうした問題が蓄積すると、ユーザーはサイト内で迷子になり、結果的に離脱率や直帰率が上昇、コンバージョン率の低下といった負のスパイラルに陥ります。
修正方法「情報構造を見直す」

最も基本的な対処法は、サイトマップを作成・更新し、コンテンツの優先順位を整理することです。当時も「コンテンツの優先度づけ」が大切だと考えられていました。今でも同様で、ユーザーが求める情報を上位階層に配置し、ナビゲーションメニューやフッター、サイドメニューなどを最適化することが求められます。
URLやフォルダ構造(パス)が乱雑であれば、アクセス解析を用いて不要なページや重複するコンテンツを整理し、内部リンクを適正化することが有効です。
もう一つの方法は、全面リニューアルです。
これは、デザインや情報構造、全体のトーン&マナーを一新する方法で、ページ数が膨大な場合でも、段階的なリニューアルが可能です。当時から「全面リニューアルは効果的」と述べていますが、2024年現在も、抜本的な見直しは時に有効です。ただし、今は段階的な試験導入(A/Bテスト)やユーザーテストを行いながら改善する手法が主流になっています。
当時の考え方と、今のSEO/UX視点との比較
2014年当時
情報量が増えすぎて分かりにくい場合は、サイトマップやメニューの整理、場合によっては全面リニューアルを行うべきとの主張が中心でした。UXという概念が徐々に浸透しつつありましたが、まだ「検索エンジン視点」や「コンテンツ数によるSEO効果」が重視されていた面もありました。
2024年現在
情報整理やUI/UX改善は、SEO対策そのものと密接に関わっています。Googleをはじめとした検索エンジンは、ユーザーが求める情報に素早くアクセスできるサイトを高く評価する傾向が強まっています。
また、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)が重要視されており、信頼できる情報源としてのサイト構造を整えることが、検索順位向上にもつながります。
間違っていた部分や不足していた点の指摘
当時の記事自体には大きな誤りはありませんが、「全面リニューアルが一番効果的」という表現は、ケースバイケースと言えます。大規模サイトでは、段階的な改善やユーザーテストを行うことで、ユーザーファーストな設計への移行がスムーズに行えます。
また、「情報整理=SEO対策」に直接結びつくとまでは当時言及されていませんでしたが、現在は情報体系の明確化、内部リンク構造の整備、モバイルフレンドリーなデザインなどがSEO要因としてより強調されています。
まとめ
当時から指摘されていた「情報整理」と「ユーザーインターフェース(UI)最適化」は、今も変わらず重要です。むしろ、2024年現在はユーザーエクスペリエンス(UX)が検索エンジン評価にも深く関与し、情報整理とナビゲーション改善は不可欠なSEO施策として定着しています。
ホームページを運用する際は、コンテンツをただ増やすだけではなく、定期的に情報構造やUIを見直し、ユーザーが求める情報にスムーズにアクセスできる設計を維持・改善し続けることが、長期的な成果(アクセス増・問い合わせ増)につながります。
おすすめの記事
大阪のホームページ制作会社TREVOでは、最短2日で仮サイトを公開できるスピード対応や、SEO対策に強いオリジナルデザインの制作サービスを提供しています。
関連の記事
-

衣川知秀
-

WordPressで制作したサイトを簡単に多言語対応させるプラグイン
衣川知秀
-

TREVOスタッフ
-

板浪雅樹
-

TREVOのホームページをリニューアルする準備をはじめています。
TREVOスタッフ
-

板浪雅樹










